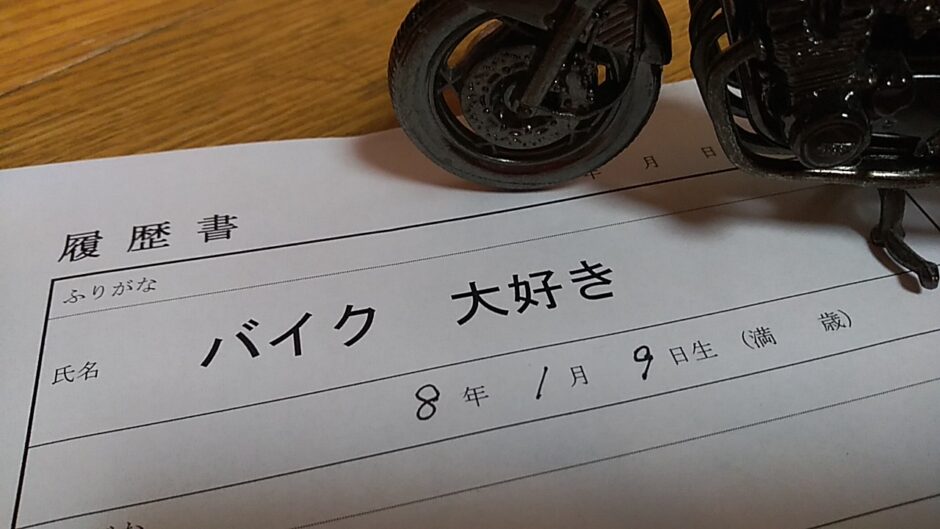最近、メディアのニュースを聞き流していると働く人が転職しやすいように法改正が進められるとかで、やたらリスキリングなどといったキーワードを耳にします。
そんな話題から読みとれるのは、職業を選び直すための転職が今までと違って若い人だけでなく、わりと広い世代に渡っても間口が開かれそうだということ。
その転職について意識したとき、準備段階で用意することになる履歴書ですが昨今では転職エージェントにWeb登録する形であらかじめ作成しておくシステムも珍しくない模様です。
そのキャリアアピールのためにも使われる履歴書に、「趣味はバイク」と書くことについて焦点を当ててみます。
履歴書に書くバイクの趣味はどんな印象か
社会人として経験が多くなってくると、履歴書は提出する側だけでなく拝見する側の立場になることも少なくないことでしょう。
今回は履歴書を作成する立場の側に立った意見としてまとめてみることにします。
このバイクの趣味を履歴書に書いたときの受け止められ方は、当人の年齢や世代によって異なるとも言えそうです。
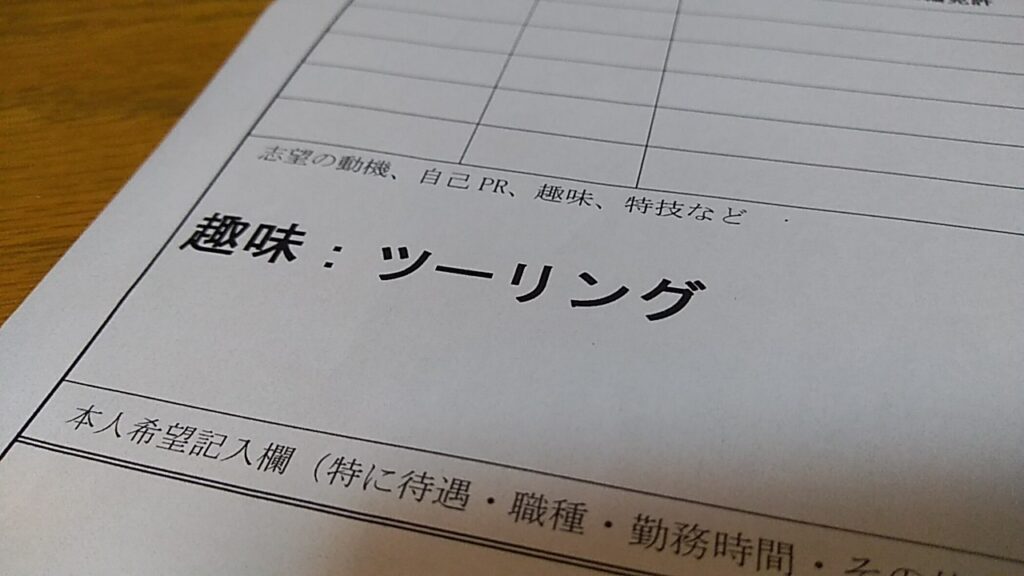
たとえば、最近の20~30代の人が「趣味はバイクです」と書いた場合、この応募者は活動的でアクティブなタイプの人かなと受け止められそうです。
もちろん、面接時に外見から受ける印象と照らして評価されるということを前提としてではあります。
見た目は地味なゲーマーなのに趣味がバイクとあったら、他にも何かもってそうな人材に見えそうです。
対して、そこそこ経験のあるベテラン社会人が同じことを書いても、バイクが趣味なのは良いが、この人はどんなスキルを持っていて何が出来る人なのかということが重要だったりします。
この場合、履歴書の自己アピール欄には趣味ではなく添付した職務経歴書へ興味を持たせるための文言や伏線のようなものが必要になってきそうです。
また、採用担当者によってはバイクにネガティブなイメージを持っていることも想定され、特にバイクのことを正直に主張しなければならないわけでもなく、面接で趣味について聞かれたとしても他に興味を持っていることについて話しておくほうが無難かもしれません。
「実はバイクが好きなんです」そう伝えるのは、採用が済んでその組織に慣れてきたころで十分でしょう。
好印象を受けない理由があるならそれは・・
バイクという乗り物に好印象を受けない人がいるとするなら、その理由はバイクに乗る本人もたやすく想像できることと思います。
道路が渋滞しているときに、停止している車の間を無理なスピードで追い抜いていくバイクはどうにも悪く目立ちます。
必要以上に大きな音たてるマフラーを装着して町中を遠慮なく走行するバイクを見ると、同じバイク乗りでもいい感じはしないもの。
乗り物のルールやマナーに限らず、道徳的なことに関する受け止め方は人によって過敏に反応されてしまうことがあります。
極端なたとえ話ですが、赤い服を着ている人が道でポイ捨てをしている人がいたら、それを見た人が他の赤い服を着ている人を見てポイ捨てする人とは簡単には思わないでしょう。
それが、赤い服を着て派手な頭髪の人という似た格好の二人が、それぞれ別な場所でポイ捨てしているのを見かけた場合はどうでしょう。
こんな感じの人は「ポイ捨てしちゃう可能性の高い人」と思いこんでしまう人がいても不思議ではありません。
自分の場合は、バイク歴が長いせいで気にしすぎかもしれませんが、良くも悪くも他のバイク乗りと同じ目線、同じ対象と片づけられることがあるというのは事実ではないでしょうか。
資格や免許の欄に二輪と書くこと
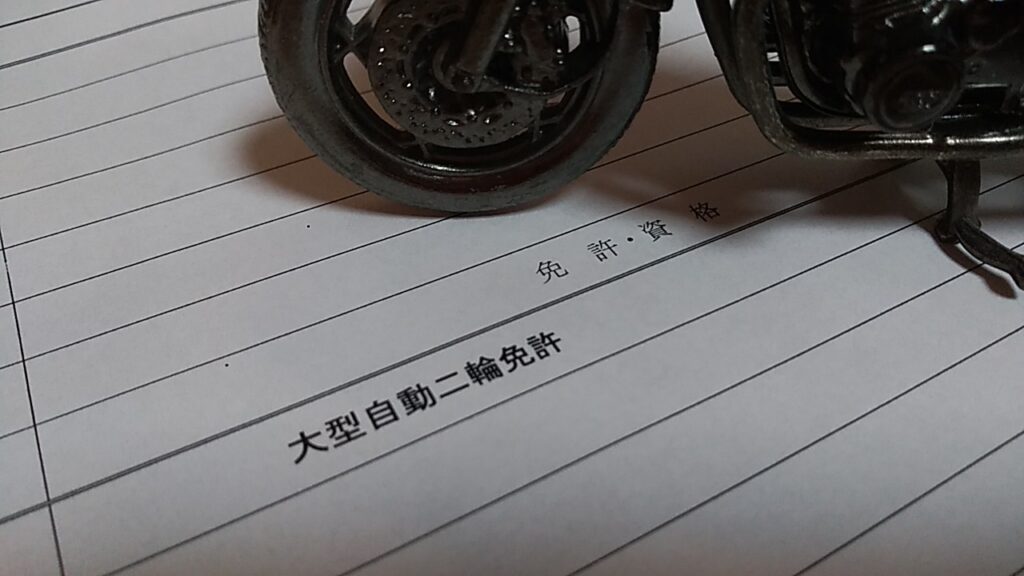
大好きなバイクが、自分にとって自己表現の一つだと思うなら自己アピールにとどまらず資格や免許の欄に二輪免許の取得を記入しておきたいところです。
ただし、これについても「好きなことに挑戦して得た成果」という前向きな評価をしてもらえるのは、先にも書いたとおり他に期待できる将来性を多分にもった人でしょう。
もっとも、その辺を自由に書いた程度で間引きの対象にしてしまう企業ならそもそも採用にならなくて良かったとも言えそうです。
話が履歴書に偏りすぎてきたところですが、どんなに立派な履歴書が仕上がったところで自分の愛車(バイク)へは何一つ良い効果はありません。
所詮、企業への応募は全て採用担当者の価値観や性格によって片づけられると思っていた方がいっそのこと気が楽なことでしょう。
社会経験が長くなるにつれ、自分を上手に表現するしたり意見を主張する前に先に守りに入る思考が良い意味で身につくようです。
ただ、バイクに乗っている間だけは不自然に身についてしまった社会性は一切置き去りにして走りと爽快感に没頭したいものです。
たとえ誰かに認められなくても、バイク好きにとって自分を表現できる楽しい時間がそこにあるのは間違いないでしょう。
キックでエンジンが始動したその瞬間から。